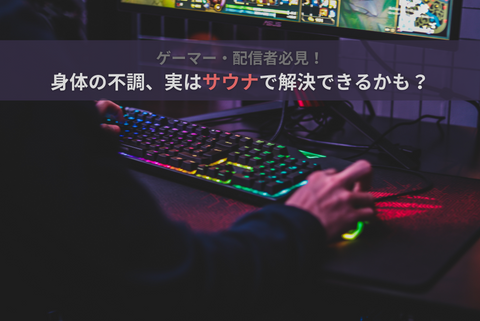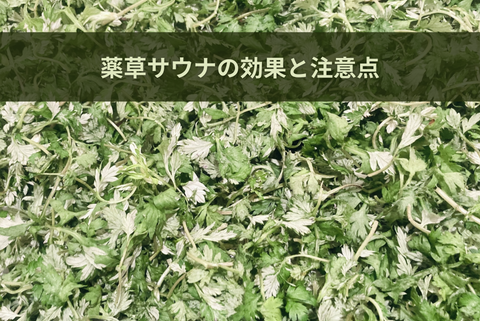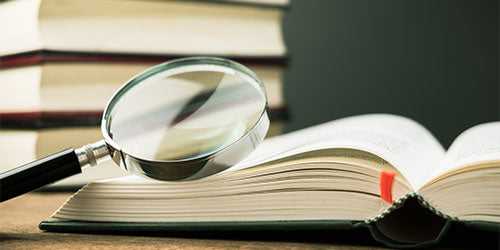サウナに行くと逆に疲れるのはなぜか?次の日がだるい原因と対策を解説

はじめに

「サウナで気分爽快!」「疲労回復効果を実感!」と感じる一方で、「なぜか体がだるい」「疲労感が残る」といった経験をされたことはありませんか?
サウナは心拍数の上昇や発汗によって体のエネルギーを消費するため、ある程度の疲労感は自然なものです。(これが良質な睡眠につながる一因でもあります)
しかし、通常以上に強い疲労感を感じる場合、それには明確な原因があります。そして適切な対策を講じることで、この過度な疲労感を軽減することが可能なのです。
この記事では、「サウナに行ったのに疲労回復どころか逆に疲れてしまう」という方や、「サウナでの疲労を最小限に抑える方法」を知りたい方に向けて、その原因と効果的な対策を詳しく解説していきます。
サウナで疲れを感じる主な原因
サウナ後に過度な疲労を感じる主な原因は以下の4つです。それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。
水分不足
サウナでの大量発汗により体内の水分が失われ、血行不良を引き起こします。これにより疲労感が増大します。
外気浴不足
サウナ後の適切な休息不足が自律神経バランスの乱れや体温調整不足を引き起こし、疲労感につながります。
長時間の利用
サウナを長時間利用することで心身に過度な負荷がかかり、エネルギーを消耗しすぎてしまいます。
既存の疲労蓄積
日常生活で既に疲労が蓄積されている状態でサウナを利用すると、さらに疲労が増加することがあります。
原因1:水分不足による血行不良
サウナ後に強い疲労感を感じる方は、体内の水分量が不足している可能性があります。
サウナでは約300~500mlもの水分が汗として失われます。水分量が減少すると、血液量の減少、血液粘度の上昇、脱水による血管収縮などが起こり、血行が悪化します。
血行不良は酸素や栄養素の供給を妨げ、疲労感を増大させるだけでなく、筋肉疲労の回復も遅らせてしまいます。
POINT
サウナでの脱水は見た目では分かりにくいことがあります。喉の渇きを感じなくても、体は既に水分不足に陥っている可能性があります。
原因2:外気浴不足による調整不足
サウナ後の外気浴や休憩が不十分だと、身体は疲れやすくなります。この原因に該当する方が最も多いのではないかと考えられます。
外気浴不足が疲労を引き起こす主な理由は以下の2つです:
理由1:自律神経の調整不足
サウナや水風呂では、熱さや冷たさの刺激によって交感神経(興奮状態)が優位になります。十分な外気浴を取ることで、副交感神経(リラックス状態)が優位になり、自律神経のバランスが回復します。
しかし外気浴が不十分なまま日常に戻ると、交感神経優位の状態が続き、身体が興奮状態のままとなるため、疲労感が増します。
理由2:体温の調整不足
水風呂やシャワーによって冷やされた体温は、外気浴を通じて徐々に正常に戻っていきます。
外気浴が不十分だと体温が冷えたままになり、疲労感が増すだけでなく、免疫力低下による風邪のリスクも高まります。
原因3:長時間サウナを利用している
サウナの長時間利用は心身に大きな負荷をかけ、特に限界の暑さに耐えることは膨大なエネルギーを消費します。
この"長時間"の基準は個人差があります。「もう少し頑張ろう」「もっとととのいたい」という気持ちから無理をすると、かえって疲労感が増してしまうことに。
サウナ施設などで示される時間はあくまで目安であり、個人によっては短い時間でも十分な効果を得られます。
疲労感が残りやすい方は、自分に最適なサウナ時間や回数を見直す必要があるかもしれません。
原因4:過度な疲労が溜まっている
日常的に身体を酷使したり、ストレスの多い環境にいる方は、既に疲労が蓄積されている状態です。そのような状態でサウナを利用すると、さらに疲労が増加することがあります。
通常の睡眠時間では回復しきれず、翌日まで疲労感が残ってしまうこともあるのです。
サウナ後の疲労を防ぐ効果的な対策

では、サウナによる過度な疲労を防ぐための具体的な対策を見ていきましょう。
| 対策 | ポイント |
|---|---|
| 1 水分補給の徹底 | サウナ前後の適切な水分補給とミネラル摂取。カフェインやアルコールには注意。 |
| 2 外気浴の見直し | 適切な場所で最低10分以上の休息をとり、自律神経と体温の調整を。 |
| 3 時間・回数の最適化 | 個人に合ったサウナ時間と回数を見つけ、無理をしない。 |
| 4 サウナタイプの変更 | 高温サウナではなく、ミストサウナや岩盤浴などの低温サウナを検討。 |
対策1:適切な水分補給を徹底する
サウナでは大量の汗をかくため、入浴前後にしっかりと水分を補給することが重要です。
汗と一緒に失われるのは水分だけではありません。ビタミン、ミネラル、電解質なども不足しがちになります。
サウナ後の疲労感を感じる方は、まず水分補給を見直してみましょう。水分補給には、ミネラルウォーターやスポーツドリンクがおすすめです。
注意!
サウナ後のアルコールやカフェインには注意が必要です。これらには利尿作用があり、体内の水分をさらに失わせてしまいます。飲む際は十分な水分補給を行った後にしましょう。
対策2:外気浴の場所と時間を見直す
適切な外気浴は自律神経と体温の調整に不可欠です。以下のポイントに注意しましょう:
- 場所の選択 - 暑すぎず寒すぎない快適な環境を選ぶ
- 季節に応じた調整 - 夏は涼しく冬は温かい場所を選ぶ
- 時間の確保 - 最低でも10分以上の休息時間を取る
必ずしも屋外で外気浴を行う必要はありません。季節や天候によっては、お風呂の縁やエアコンの効いた脱衣所の椅子など、快適に過ごせる室内で休息するのも良い選択です。
対策3:サウナの時間と回数を最適化する
サウナでの長時間の滞在は体に大きな負荷をかけます。「もっと気持ち良くなりたい」という気持ちは理解できますが、長時間のサウナはかえって疲労を増大させることもあります。
自分に合った適切な入浴時間とセット数を見つけましょう。一般的には2〜4セットが「ととのい」に最適とされていますが、それ以上のセット数は体に過度な負荷をかけることになります。
サウナの効果を最大限に引き出すためには、自分の体調や感覚に合わせた時間と回数を見つけることが重要です。
対策4:低温サウナを選択する
日本では高温のドライサウナが主流ですが、ミストサウナや遠赤外線サウナ、岩盤浴などの低温サウナも選択肢の一つです。
疲労感を最小限に抑えつつリラックス効果を得たい方は、低温のミストサウナや遠赤外線サウナがおすすめです。
高温サウナから低温サウナへの切り替えは、最初は物足りなさを感じるかもしれませんが、自分の体調に合わせたサウナタイプを選ぶことで、より効果的に心身をリラックスさせることができます。
自宅サウナで最適なサウナ体験を
これまで紹介してきた対策は効果的ですが、公共のサウナ施設では思い通りの環境を作ることが難しい場合もあります。そんな時に便利なのが自宅サウナです。
自分のペースで楽しめる
時間を気にせず、体調に合わせた最適な時間と温度でサウナを楽しめます。疲労感を感じたらすぐに休憩することも可能です。
理想的な水分補給
お気に入りのドリンクを用意し、最適なタイミングで水分補給ができます。電解質バランスを考えた飲み物も準備可能です。
完璧な外気浴環境
快適な温度と空間で、十分な休息時間を確保できます。季節や天候に左右されず、理想的な外気浴を実現できます。
長期的なコスト効率
初期投資は必要ですが、頻繁にサウナ施設に通う費用と比較すると、長期的には経済的。何より健康投資としての価値があります。
idetoxでは、さまざまなタイプの高品質家庭用サウナを取り揃えています。自分に合った温度やスタイルのサウナを自宅に導入することで、疲労感を最小限に抑えながら、サウナの素晴らしい効果を最大限に享受できます。
まとめ
サウナ後の過度な疲労感は、適切な対策で軽減することができます。主な対策をおさらいしましょう:
- 水分補給を徹底する - サウナ前後の適切な水分と電解質の補給
- 外気浴を充実させる - 十分な時間と快適な環境での休息
- 適切な時間とセット数を守る - 自分に合った最適なサウナ利用
- 必要に応じてサウナタイプを変える - 低温サウナの活用
これらの対策を実践すれば、「サウナによる疲労」よりも「サウナで得られる素晴らしい効果」を実感できるようになります。そして自宅サウナなら、これらの対策をさらに効果的に実践できるでしょう。
疲労感を気にせず、サウナライフを思う存分楽しむための第一歩として、ぜひこれらの対策を試してみてください。
SNSでシェアする
RECOMMEND BOX SAUNA
-
![バレルサウナ | ベーシック | IDOB-1812 | 2-10人用 | 12サイズ | 選べる木材]()
バレルサウナ | ベーシック | IDOB-1812 | 2-10人用 | 12サイズ | 選べる木材
- 通常価格
- ¥498,000~ (税込)
- セール価格
- ¥498,000~
- 通常価格
-
- 単価
- あたり
-
![屋外サウナ | オーダーメイド | J-ALP-2020P | シャワールームオプション | 自宅サウナ]()
屋外サウナ | オーダーメイド | J-ALP-2020P | シャワールームオプション | 自宅サウナ
見積り対象商品
-
![屋外サウナ | オープンスカイサウナ | 2人用 | J-WSD-1818LT | Bluetoothスピーカー | 自宅サウナ]()
屋外サウナ | オープンスカイサウナ | 2人用 | J-WSD-1818LT | Bluetoothスピーカー | 自宅サウナ
- 通常価格
- ¥1,480,000~ (税込)
- セール価格
- ¥1,480,000~
- 通常価格
-
- 単価
- あたり
-
![バレルサウナ | パノラマビュー | IDOP-1815 | 2-10人用 | 11サイズ]()
バレルサウナ | パノラマビュー | IDOP-1815 | 2-10人用 | 11サイズ
- 通常価格
- ¥648,000~ (税込)
- セール価格
- ¥648,000~
- 通常価格
-
- 単価
- あたり
-
![バレルサウナ | 薪ストーブ付 | 2-4人用 | ハーフガラス | 選べる木材]()
バレルサウナ | 薪ストーブ付 | 2-4人用 | ハーフガラス | 選べる木材
- 通常価格
- ¥1,268,000~ (税込)
- セール価格
- ¥1,268,000~
- 通常価格
-
¥5,550(税込) - 単価
- あたり
-
![ヒノキ製バレルサウナ | OBT-1824H | パノラマビュー | 最大4人用]()
ヒノキ製バレルサウナ | OBT-1824H | パノラマビュー | 最大4人用
- 通常価格
- ¥1,298,000 (税込)
- セール価格
- ¥1,298,000
- 通常価格
-
- 単価
- あたり
-
![屋外サウナ | サウナ小屋 | J-WSD-LT08 | シャワールーム付 | 4人用 | 自宅サウナ]()
屋外サウナ | サウナ小屋 | J-WSD-LT08 | シャワールーム付 | 4人用 | 自宅サウナ
- 通常価格
- ¥4,780,000~ (税込)
- セール価格
- ¥4,780,000~
- 通常価格
-
- 単価
- あたり
-
![バレルサウナ | ビューモデル | IDOC-1812 | サンルーフ付 | 2-10人用 | 12サイズ]()
バレルサウナ | ビューモデル | IDOC-1812 | サンルーフ付 | 2-10人用 | 12サイズ
- 通常価格
- ¥548,000~ (税込)
- セール価格
- ¥548,000~
- 通常価格
-
- 単価
- あたり
-
![屋外サウナ | オープンスカイサウナ | 4人用 | J-WSD-1817LT | Bluetoothスピーカー | 自宅サウナ]()
屋外サウナ | オープンスカイサウナ | 4人用 | J-WSD-1817LT | Bluetoothスピーカー | 自宅サウナ
- 通常価格
- ¥1,980,000~ (税込)
- セール価格
- ¥1,980,000~
- 通常価格
-
- 単価
- あたり
-
![バレルサウナ | 3-4人用 | 薪ストーブ付属 | コンパクト | 自宅サウナ]()
バレルサウナ | 3-4人用 | 薪ストーブ付属 | コンパクト | 自宅サウナ
- 通常価格
- ¥998,000~ (税込)
- セール価格
- ¥998,000~
- 通常価格
-
¥3,468(税込) - 単価
- あたり
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。