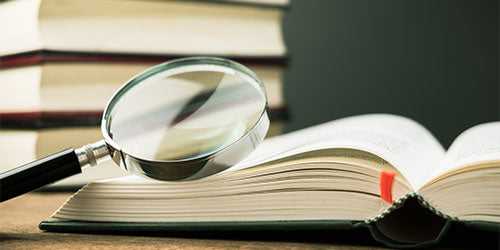スマホ依存症の恐ろしさ | 症状から対策まで徹底解説

スマホ依存症の恐ろしさ|症状から対策まで徹底解説
はじめに
「スマホを手に持っていないと不安になる」
「スマホゲームをしていて気がついたら朝だった」
「スマホが電池切れになると、イライラしたり、落ち着かなくなったりする」
「やるべきことがあるのに、つい後回しにしてスマホを触ってしまう」
多かれ少なかれ、当てはまるという方も少なくないのではないでしょうか。
そんな方は、「スマホ依存症」と呼ばれる状態に近づいているかもしれません。
スマホの利便性の高さは言うまでもありません。
もはやスマホなしの生活が難しい時代ですが、この便利な道具に頼りすぎると、副作用も多く注意が必要です。
スマホ依存症は単なる使いすぎではなく、心身の健康や日常生活に深刻な影響を与える可能性があります
本記事では、スマホ依存症の症状から脳や身体への影響、そして効果的な対策方法まで徹底解説します。
スマホ依存症とは

スマホ依存症とは、「スマートフォンの使用を続けることで昼夜逆転する、成績が著しく下がるなど様々な問題が起きているにも関わらず、使用がやめられず、スマートフォンが使用できない状況が続くと、イライラし落ち着かなくなるなど精神的に依存してしまう状態」を指します。
- スマホが手元にないと不安になる
- SNSやメールを必要以上に確認する
- 食事中や会話中もスマホを見てしまう
- スマホの充電切れに大きな不安を抱く
- 歩きスマホが習慣になっている
厚生労働省の調査によると、2013年時点で成人約421万人、13〜18歳の若者約52万人がスマホ・インターネット依存の傾向にあるとされ、2008年の調査と比較して1.5倍に増加しました。
それから10年以上が経過し、スマホの普及率はさらに高まり、アプリケーションの充実も加速しています。また、コロナ禍の影響でひとりの時間が増えたことから、依存症傾向の人数はさらに増加していると考えられます。
POINT
スマホ依存症は実生活に支障をきたすことが特徴で、自分が依存していることに気づいていない人も多くいます。依存状態が長引くと引きこもりなど、より深刻な問題につながる可能性があります。
スマホ依存症の恐ろしい影響
「便利だから手放せないスマホ。依存して何が悪いの?」
そう思う方も多いのではないでしょうか。しかし、スマホ依存症は様々な専門家が指摘するように、心身に深刻な影響を与える可能性があります。
影響①:脳の萎縮と認知機能の低下
スマホ依存の傾向が長く続くと、脳の特定部位の萎縮が進むことが複数の研究で指摘されています。
- 自分や相手の感情の読み取りに関わる部分
- 注意力、記憶力などの認知機能に関わる部分
特に脳の発達途上にある思春期・青年期では、その影響がより大きいと考えられています。この年代でスマホ依存に陥ると、豊かな体験や学習する機会を失うことにつながります。
影響②:記憶力の低下
スマホから得られる情報量が多いと脳の疲労が起こりやすくなり、記憶力や集中力に悪影響を及ぼします。
勉強や仕事、食事などをしている途中でスマホ操作をすることは、マルチタスクや情報過多を引き起こします。また、スマホのアプリでスケジュールやメモをしている場合、「デジタル健忘症」と呼ばれる現象を引き起こす可能性もあります。
影響③:上半身の不調
スマホを長時間使用すると、下を向く姿勢が続くため、首や肩の筋肉にストレスがかかり、血流が悪くなります。
- 肩こり・首の痛み
- ストレートネック(スマホ首)
- 腰痛
- 猫背・巻き肩
「ストレートネック」とは首の骨がまっすぐになってしまう状態で、本来は緩やかなカーブを描いている首の骨が変形することで、頭痛やめまいなどの症状を引き起こす可能性があります。
影響④:目の不調
長時間スマホの画面を見続けることは、様々な目の問題を引き起こします。
- 眼精疲労
- スマホ老眼
- ドライアイ
特に「スマホ老眼」は20代、30代の若い世代でも発症することがあり、目のピント調整機能が低下することで起こります。また、スマホ使用中は瞬きの回数が減少し、ドライアイの原因になることも指摘されています。
影響⑤:睡眠の質の低下
スマホに触れる時間が長いと、情報量や画面の明るさによって脳が疲弊し、なかなか寝付けなくなることがあります。特に寝る前のスマホ操作が習慣となっている場合、脳が昼と夜を正しく認識できなくなり、睡眠リズムが崩れやすくなります。
睡眠の質の低下は、集中力の低下や体調不良、さらには免疫力の低下にもつながる可能性があります。
影響⑥:うつ病などの精神疾患
脳・身体の疲労が原因で、睡眠障害・イライラ・不安感が強くなり、ひどい場合、うつ病などの精神疾患を発症することもあります。
スマホを使用するとき、SNSやニュースを通して社会や人間関係に触れることになりますが、SNSでの他者との比較や、常に更新される情報への追従が精神的ストレスとなり、精神疾患を誘発するケースも報告されています。
影響⑦:事故のリスク
「ながらスマホ」は重大な事故を引き起こす可能性があります。
- スマホ操作しながらの車の運転
- スマホゲームをしながらの自転車走行
- 歩きスマホによる転倒や駅ホームからの転落
スマホの画面に気を取られると、周囲への注意力が低下し、自分だけでなく他者も巻き込む重大な事故につながるリスクがあります。
子どもに広がるスマホ依存症

小中高生のスマホ所持率が年々高まり、スマホ依存症は成人だけでなく、若年層への拡がりも大きな社会問題となっています。
注意!
子どもは自制心が未熟な場合が多く、セルフコントロールがうまくできないことがあります。その結果、目の前のスマホに夢中になり、勉強や通学、食事や睡眠をおろそかにするケースが増えています。
特に子どもの場合、以下のようなリスクが高まります:
- 学力の低下と学校生活への支障
- 生活リズムの乱れ(昼夜逆転など)
- コミュニケーション能力の発達不全
- 課金トラブルや犯罪被害のリスク
- 脳の発達への悪影響
一方で、スマホは使い方次第では学力向上のツールとして、また自分の頭で考えて行動する主体性を磨くツールとしても高い機能を発揮します。
子どもがスマホ依存症になることを防ぐためには、保護者が適切に使用方法を指導し、寄り添うことがますます重要になっています。
スマホ依存症の予防と対策

スマホ依存症を予防・改善するための効果的な対策をご紹介します。
対策①:スマホから離れる時間を意識的につくる
基本的な対策は、スマホから離れる時間を意識的につくることです。具体的なルールを設定し、それを習慣化することが重要です。
- 「スマホを1時間触ったら、次の1時間は触らない」
- 「食事中はスマホを触らない」
- 「就寝前2時間はスマホを使用しない」
- 「枕元にスマホを置かない」
最近のスマホには、使用時間の制限や特定アプリの使用を制限する機能も搭載されています。これらの機能を活用して、自分自身の使用時間を管理することも効果的です。
対策②:リアルな人間関係や活動を充実させる
人と直接会って会話したり、体を動かしたりする時間を増やすことで、自然とスマホから離れる時間を作ることができます。
- 趣味活動への参加
- 運動やスポーツの実施
- 友人や家族との時間を大切にする
- 読書や創作活動など、スマホを使わない趣味を持つ
スマホ上の情報だけでなく、人と触れ合うことで得られる情報、体を動かすことによって得られるリフレッシュ効果をバランスよく取り入れましょう。
対策③:家庭内でのスマホ使用ルールを定める
特に子どものスマホ依存を防ぐためには、家庭内で明確なルールを設けることが効果的です。ただし、一方的に制限するのではなく、子どもと話し合って納得した上でルールを決めることが大切です。
- 使用可能な時間帯を決める
- 共有スペース(リビングなど)でのみ使用する
- 家族の時間(食事など)ではスマホを使わない
- 保護者が子どもの使用状況を定期的に確認する
子どもがスマホ以外の楽しみを見つけられるよう、一緒に料理やスポーツをするなど、家族で共有できる活動を増やすことも重要です。
対策④:心配なら早めに医師へ相談
依存症の兆候があり、身体的・精神的な不調を感じる場合は、早めに医師へ相談することをおすすめします。
スマホ依存症の人が増えた結果、インターネット・スマホ依存、ゲーム依存の治療を専門に行う医療機関も増えています。適切な治療を受けることで、依存状態からの回復が期待できます。
POINT
うつ病などの精神疾患にも共通しますが、本人は自分の状態に気づかないことも多いものです。家族や周囲の人が互いに見守り合う意識が重要です。
まとめ:スマホとの健全な関係を築くために
スマホ依存症の恐ろしさと対策についてご紹介してきましたが、いかがでしたか。
| スマホ依存症の主な影響 | 効果的な対策 |
|---|---|
| 脳の萎縮と認知機能の低下 | スマホから離れる時間を意識的に作る |
| 身体的不調(肩こり、眼精疲労など) | リアルな人間関係や活動を充実させる |
| 睡眠障害とそれに伴う健康問題 | 家庭内でのスマホ使用ルールを定める |
| うつ病などの精神疾患 | 必要に応じて専門家に相談する |
スマホ依存症は単なる「使いすぎ」ではなく、様々な健康上の問題や日常生活への支障を引き起こす可能性があります。スマホ依存症は身近な問題であり、本人の意識と周囲の人の見守り、そしてデジタルデトックスの時間を多く作ることの大切さを感じていただけたのではないでしょうか。
生活に不可欠なツールであるスマホとうまく付き合い、デジタルデトックスの時間も楽しめるような、バランスの取れた生活習慣を身につけていきましょう。
自宅でデジタルデトックスをお考えの方には、リラックス効果の高い自宅用サウナがおすすめです。心身のリフレッシュに効果的で、スマホから離れる貴重な時間を作り出せます。
アンケート
最後までご覧いただきありがとうございます。 より良い自宅サウナを提供するために、アンケートにご協力よろしくお願いします!質問は3つです。
SNSでシェアする
RECOMMEND BOX SAUNA
-
![バレルサウナ | ベーシック | IDOB-1812 | 2-10人用 | 12サイズ | 選べる木材]()
バレルサウナ | ベーシック | IDOB-1812 | 2-10人用 | 12サイズ | 選べる木材
- 通常価格
- ¥498,000〜 (税込)
- セール価格
- ¥498,000~
- 通常価格
-
- 単価
- あたり
-
![屋外サウナ | オーダーメイド | J-ALP-2020P | シャワールームオプション | 自宅サウナ]()
屋外サウナ | オーダーメイド | J-ALP-2020P | シャワールームオプション | 自宅サウナ
見積り対象商品 -
![屋外サウナ | オープンスカイサウナ | 2人用 | J-WSD-1818LT | Bluetoothスピーカー | 自宅サウナ]()
屋外サウナ | オープンスカイサウナ | 2人用 | J-WSD-1818LT | Bluetoothスピーカー | 自宅サウナ
- 通常価格
- ¥1,480,000〜 (税込)
- セール価格
- ¥1,480,000~
- 通常価格
-
- 単価
- あたり
-
![バレルサウナ | パノラマビュー | IDOP-1815 | 2-10人用 | 11サイズ]()
バレルサウナ | パノラマビュー | IDOP-1815 | 2-10人用 | 11サイズ
- 通常価格
- ¥798,000〜 (税込)
- セール価格
- ¥798,000~
- 通常価格
-
- 単価
- あたり
-
![バレルサウナ | 薪ストーブ付 | 2-4人用 | ハーフガラス | 選べる木材]()
バレルサウナ | 薪ストーブ付 | 2-4人用 | ハーフガラス | 選べる木材
- 通常価格
- ¥1,268,000〜 (税込)
- セール価格
- ¥1,268,000~
- 通常価格
-
¥5,550(税込) - 単価
- あたり
-
![ヒノキ製バレルサウナ | OBT-1824H | パノラマビュー | 最大4人用]()
ヒノキ製バレルサウナ | OBT-1824H | パノラマビュー | 最大4人用
- 通常価格
- ¥1,298,000〜 (税込)
- セール価格
- ¥1,298,000
- 通常価格
-
- 単価
- あたり
-
![屋外サウナ | サウナ小屋 | J-WSD-LT08 | シャワールーム付 | 4人用 | 自宅サウナ]()
屋外サウナ | サウナ小屋 | J-WSD-LT08 | シャワールーム付 | 4人用 | 自宅サウナ
- 通常価格
- ¥4,780,000〜 (税込)
- セール価格
- ¥4,780,000~
- 通常価格
-
- 単価
- あたり
-
![バレルサウナ | ビューモデル | IDOC-1812 | サンルーフ付 | 2-10人用 | 12サイズ]()
バレルサウナ | ビューモデル | IDOC-1812 | サンルーフ付 | 2-10人用 | 12サイズ
- 通常価格
- ¥548,000〜 (税込)
- セール価格
- ¥548,000~
- 通常価格
-
- 単価
- あたり
-
![屋外サウナ | オープンスカイサウナ | 4人用 | J-WSD-1817LT | Bluetoothスピーカー | 自宅サウナ]()
屋外サウナ | オープンスカイサウナ | 4人用 | J-WSD-1817LT | Bluetoothスピーカー | 自宅サウナ
- 通常価格
- ¥1,980,000〜 (税込)
- セール価格
- ¥1,980,000~
- 通常価格
-
- 単価
- あたり
-
![バレルサウナ | 3-4人用 | 薪ストーブ付属 | コンパクト | 自宅サウナ]()
バレルサウナ | 3-4人用 | 薪ストーブ付属 | コンパクト | 自宅サウナ
- 通常価格
- ¥998,000〜 (税込)
- セール価格
- ¥998,000~
- 通常価格
-
¥3,468(税込) - 単価
- あたり
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。